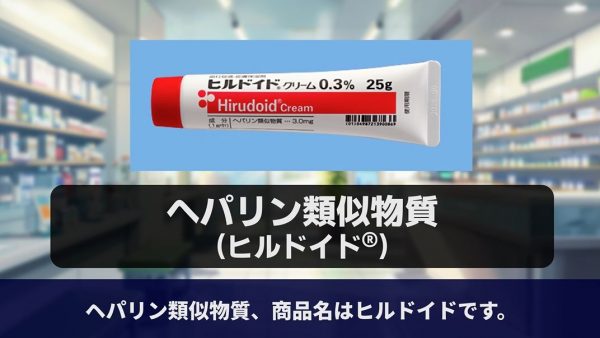ヘパリン類似物質こと保湿剤の「ヒルドイド」ってどんな薬? そもそものヘパリンの作用や、クリームと油性クリームの違いについて解説してみた
2025年09月11日11時00分 / 提供:ニコニコニュース![]()
今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『【解説】『どうして血液凝固阻止剤が保湿剤になるの?!』 ヘパリン類似物質(ヒルドイド) 【宮舞モカのお薬ラジオ #57】』といういわし@超ビビリさんの動画です。
投稿者メッセージ(動画説明文より)
定期的に、1つのお薬を取り上げて詳しく解説する企画です。 いいねを押すとプチお薬解説を見ることができます。
ヘパリン類似物質、商品名ヒルドイドについて薬剤師である投稿者のいわし@超ビビリ(休養中)さんが解説します。
類似物質ということで、まずは元のヘパリンという物質の解説から。ヘパリンは人間の肝臓で作りだされる、主に血液凝固を阻止する物質です。ヘパとはギリシャ語で肝臓の意味なのだとか。
人体が出血したとき、まずはそこに血小板が集まり一次血栓を作ります。次にそこにフィブリンという物質が集まり補強を行うとのこと。
そのフィブリンは、トロンビンという物質により体内でフィブリノーゲンから変換されて作られます。
一方で体内にはアンチトロンビンという、トロンビンを阻害して血液凝固を抑える物質もあります。ただしアンチトロンビンの力はとても弱いのだそう。しかしヘパリンと組むと構造を変化させて強力にトロンビンを阻害できるようになります。
という流れで、ヘパリンは血液凝固を阻止する作用を発揮するのだそうです。
そんなヘパリンはかつて血管が血栓で詰まる「血栓症」の治療に使われていました。
しかし現在はもっと性能の良い薬が多数登場したことから、その役目は終えたとのこと。代わりに血液透析などの管の中における血液凝固を阻止したり、ワルファリンなどの抗凝固薬服用患者の手術前における代替として使われているのだそうです。
そして今回の主題であるヘパリン類似物質は、ヘパリンと似た構造を持つ物質を人工的に作り出したもの。その名の通りヘパリンと似た作用を持っているのですが、使われ方はヘパリンとまったく異なり保湿剤として使われています。
こちらがヘパリンの化学構造です。化学がわからなくても「OH」が沢山あることが見るだけでわかりますね。このOHは水と結合しやすい性質があります。そのためOHを沢山持つヘパリンは親水性が非常に高いのだそうです。これはヘパリン類似物質も同じ。水を逃さない、高い保湿作用を有します。
そんなヘパリン類似物質には様々な剤型があります。画像はクリームと油性クリームです。どう違うのでしょうか。
クリームは水と油が混ざってできるもの。その混ざり方には2種類あり、水の中に油が散在している水中油型と、油の中に水が散在している油中水型と呼びます。この水中油型がクリーム剤で、油中水型が油性クリーム剤なのだそうです。
クリーム剤は水に近い性質を持ちしっとりしてのびが良く、油性クリーム剤は油に近い性質でのびが悪くベタベタしやすいですが、効果が長持ちします。ちなみに先発品のヒルドイドでは油性クリーム剤を「ソフト軟骨」と称するのだそう。
他にローションやゲルや泡状スプレーもあります。
皮膚の乾燥でお世話になることが多いヒルドイド。ヘパリン類似物質ということから、そもそもヘパリンとは何ぞや、ということころからの丁寧な解説でした。また、剤型ごとの特徴や使い方については動画内で詳しく紹介されていますので、興味を持たれた方はどうぞ動画をご視聴ください。
視聴者のコメント
・平素より大変お世話になっております
・思ってた、これ思ってたw
・ちょっとはたらく細胞見返してくる!
・ヒドロキシ基がこれでもかと
・はえー、使い勝手がええんやね
・ためになったわ
▼動画はこちらから視聴できます▼
『【解説】『どうして血液凝固阻止剤が保湿剤になるの?!』 ヘパリン類似物質(ヒルドイド) 【宮舞モカのお薬ラジオ #57】』
―あわせて読みたい―
・睡眠薬の副作用に「悪夢」や「金縛り」があるのはどうして? 覚醒を抑える睡眠薬「レンボレキサント(商品名:デエビゴ)」の特徴を薬剤師が解説してみた
・爆薬から心臓の薬になった「ニトログリセリン」ってどんな物質? ダイナマイト工場での誕生のきっかけや薬としての作用まで解説してみた
関連記事
- テキスト入力だけで映像生成できるAI「ToMoviee」がハロウィン動画投稿キャンペーン開催! 合計10名にオリジナル商品などをプレゼント、募集は11月4日まで
- にじさんじのライバーにどこか似ている動物マスコット「にじたうん 2ちょうめ」グッズ販売開始
- 堤防で草を食べて働くヤギを見に行ってきた! ヤギによる6日間の“除草作戦”の結果を人間の草刈りと共に紹介
- 東方Project・16キャラのコスプレで「Bad Apple!!」を演奏してみた! 博麗霊夢から伊吹萃香まで登場するフルート演奏動画が圧巻
- 『ポケモン』の新作を記念してアルミ鋳造でロゴを作ってみた! 磨き上げた金属の輝きへ「ロマンがあっていいな」「ピカ鋳」の声
ネタ・コラムカテゴリのその他の記事
- テキスト入力だけで映像生成できるAI「ToMoviee」がハロウィン動画投稿キャンペーン開催! 合計10名にオリジナル商品などをプレゼント、募集は11月4日まで
- にじさんじのライバーにどこか似ている動物マスコット「にじたうん 2ちょうめ」グッズ販売開始
- 堤防で草を食べて働くヤギを見に行ってきた! ヤギによる6日間の“除草作戦”の結果を人間の草刈りと共に紹介
- 東方Project・16キャラのコスプレで「Bad Apple!!」を演奏してみた! 博麗霊夢から伊吹萃香まで登場するフルート演奏動画が圧巻
- 『ポケモン』の新作を記念してアルミ鋳造でロゴを作ってみた! 磨き上げた金属の輝きへ「ロマンがあっていいな」「ピカ鋳」の声